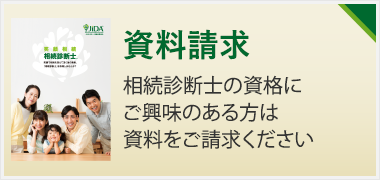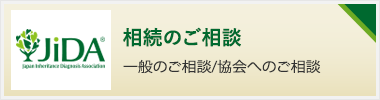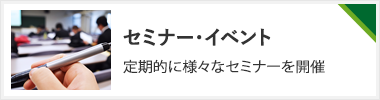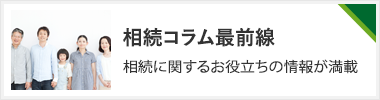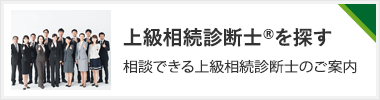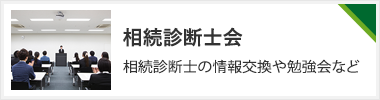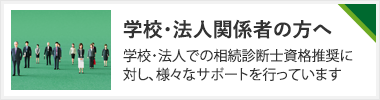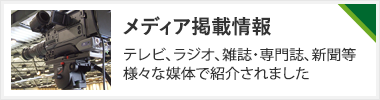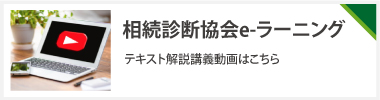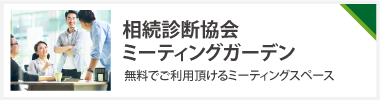【vol.111】相続Q&A~親の介護が寄与分として認められる場合とは?~

質問
兄弟の中で私だけ親の介護をしました。
相続の時に「寄与分」として認めてもらえるでしょうか?
回答
親(被相続人)を介護したことが「寄与分」(民法904条の2)として認められるのは、どのような場合でしょうか。
最終的には裁判所の判断となりますが、一般的には以下のような点がポイントとなります。
1 .介護の必要性
被相続人が「介護を必要とする健康状態にあったこと」が1つ目のポイントになります。
要介護2以上であることが目安とされることが多いようです。
2. 特別の貢献
その介護が「特別の貢献=身分関係に基づいて通常期待される程度を超えたものであること」が2つ目のポイントです。
子が親である被相続人宅に同居して生活の援助をしてもらっていたようなケースでは、「子が親を介護するのは当たり前」と見られる余地が大きくなるでしょう。
3 .無償
3つ目のポイントは「無償」。
有償(金銭に限らない広い意味での対価)であっても、後記7の介護報酬などと比べて著しく低額ならクリアしているといえるでしょう。
4. 継続
4つ目は「継続」。
単発ではなく、少なくとも数か月〜1年間程度は必要でしょう。
5 .専従
5つ目は「専従」。
気が向いた時だけやるというのではNGです。
6 .財産維持との因果関係
6つ目は「本来は有料で介護を頼まなければならないところを、家族の介護で賄うことによってお金を使わずに済んだ」などの「因果関係」の存在。
単なる「精神的な癒しになった」ではNGなのです。
7 .寄与分の金額
最後に気になる金額ですが、「介護保険制度の介護報酬」を参考に、「裁判所の裁量による掛け率」で増減されることが多いです。
教訓
相続の際に揉めないよう、親の介護を誰がやるかは兄弟姉妹でよく話し合い、協力して行いましょう。